
ついに4ヶ月に渡った大学生活が終わり、一旦落ち着きました。
応援してくださった皆様、見守ってくださった皆様、ありがとうございました^^
今回の経験を通して感じたことを少しアウトプット。
この4ヶ月、授業の中で学生の方とチームで共同作業をして、一つのテーマについて深く問い、いろんな意見を交流させながら、最終的には一つのブランドをデザインしていく、ということをしていました。
そして最後のプレゼン後に教授にフィードバックをもらったのですが、そこでもらった言葉に大きなヒントをもらったように思います。
それは「あなたには問題を解決して状況を良くしようという意思がなさすぎる」といった内容の意見でした。
確かに!!!と思いました。
それが私にとって、社会との繋がりを捉え直すきっかけになりましたし、新たな問題を作ってくれたように思います。
研究室では何度かお話ししたことがあったかと思うのですが、私には数年前から「人の役に立つ必要はあるのだろうか?」という問いがありました。
そして「悩みを解決する必要はあるのだろうか?」という問いもありました。
というのも、悩みには、悩みの価値があります。
だから私は悩んでいる人を気の毒に思うことがないし、人は変わってもいいし変わらなくてもいいと思っています。
それがその人の選んだ人生だから。
その人の「今」を尊重すると、こう思うのです。
なので私が人と積極的に関わろうと思う瞬間は、相手が明確に物事を解決しようとしていたり、自分から主体性を持って変化したいと思った時に、一緒にいれば才能をシェアするという感覚です。
「決めた人に才能を注ぐ」
これが自分にとっての社会的な働きかけでした。
決めた人が笑っていたら嬉しい。決めた人が幸せだと嬉しい。
その感覚はあるものの、もし決めた人が困難な道のりに自ら進もうとしていても、きっと止めることはありません。
その痛みは、その人の命が、感じたいものだから。
なので関連して、まだ見ぬ誰かに対して「1人でも多く困っている誰かを助けたい!」という気持ちがどうしてもピンとこないのです。
困っている人は、いま、必要性があって、困ったり悩んだりしているから。
無理に変わる必要もないし、変える必要もない。
必要善もあれば、必要悪も存在する。
その人生を尊重する、という考え方をしていると、どうしても社会と噛み合わなくなってきているのかもしれない、と感じました。
それが今回の大学プレゼンでいただいたフィードバックで、明確になったなと思います。
ということで今日は、「私たちは問題とどう付き合っていくか?」というお話をしたいと思います。
本日のテーマ
①問題はどうして起きるか?
②問題のメリット
③哲学は問題解決を超えて問題消滅を起こす
④まとめ:問題とどう付き合っていくか?
①問題はどうして起きるか?
問題って色々ありますよね。
人間関係が悪いとか、恋愛がうまくいかないとか、健康じゃないとか、お金がないとか、時間がないとか、自由がないとか。
私はこれらの問題の原因を、「抽象度が低いから(具体に寄りすぎているから)」だと思っています。
または、「抽象度の上げ方を間違えている」場合もあると思っています。
今日したいのは、抽象度の扱い方を知ることで問題はなくなって生きやすくなるけれど、問題がなくなりすぎると現代社会に噛み合わなくなっていく、というお話しです。
いつもお話ししている「エゴは極端に宿る」のお話しにも近いですね。
そもそも問題がなぜ問題になってしまうかと言うと、パズルのピースをイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。
パズルのピースには固定の形があるから、ちょっとでも形が違うと、噛み合いませんよね。
噛み合わないと歪になってしまう。
その「歪み」を私たちは「問題」と捉えます。
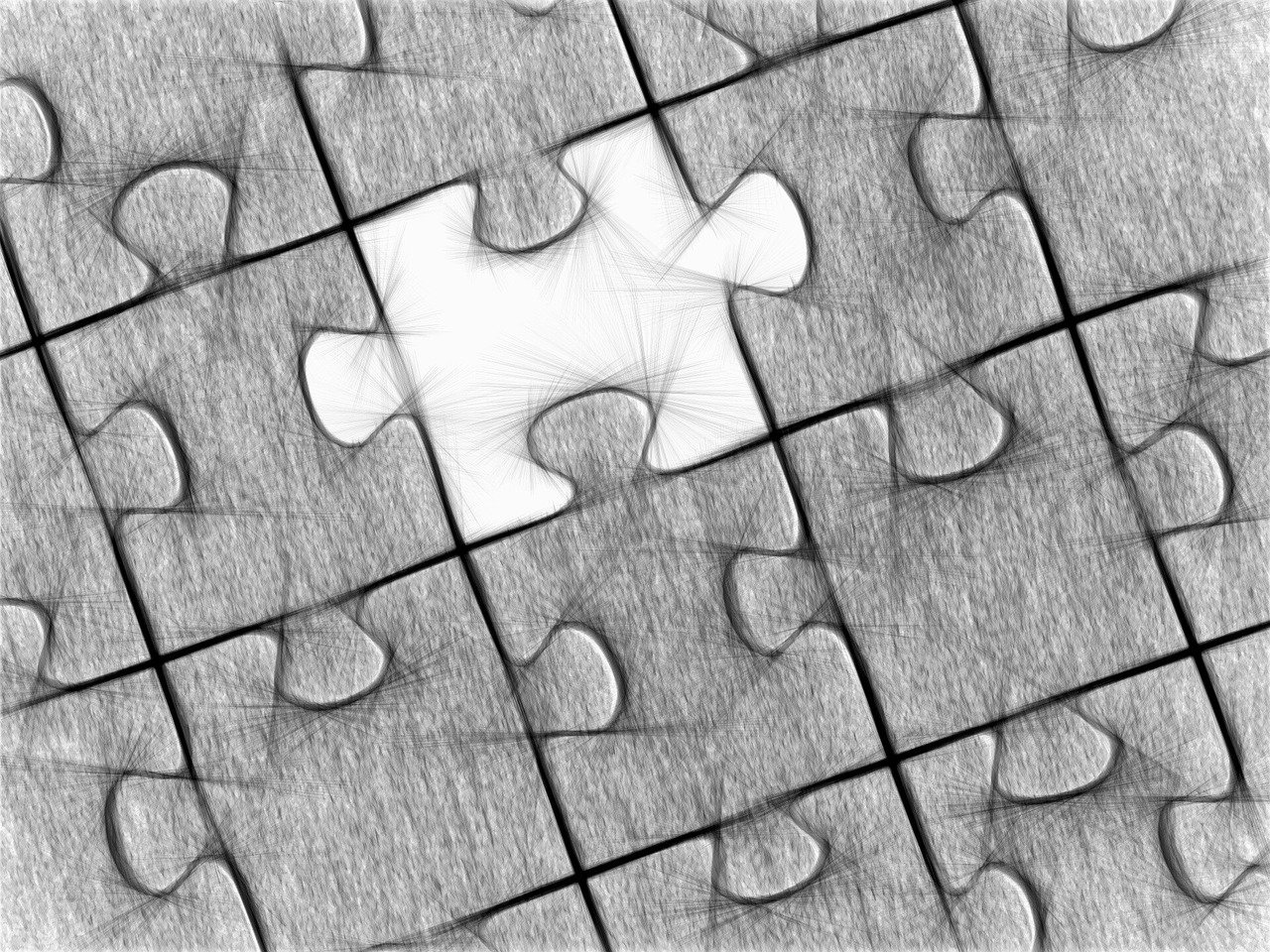
言葉が通じない、相手の気持ちがわからない、価値観の違いがある、夢や目標が叶わない、お金が足りない、病気になってしまう、愛されない、愛することができない。
これは全て物事の「具体性」に注目して「歪み」を発見した結果です。
テストの点数が悪いとか、付き合うとか付き合わないとか、浮気とか不倫とか、結婚とか離婚もそうですよね。
「理想」のパズルのピースに「現実」が合わないことに対して「ネガティブな意味づけ」をすることから、不快が生まれているように思います。
そして物事を具体的に細かく捉えて、パズルのピースを綺麗に当てはめようとするほどに「はまらない」という問題は生まれるし、問題を解決するための方法は限定されていくのです。
ある抽象度で生まれた問題には、同じ抽象度の解決策をあてがうことが求められます。
例えば「結婚したいのにできない」という人の問題を解決するには、同じ抽象度の「結婚する」という解決策が必要になります。
「恋人がいる」「結婚しなくても幸せ」とかでは満足できなくて、自分が望む解決策の抽象度が「結婚」に絞られているから、その解決策の抽象度が合わないと、満足しないのです。
だからこそ、「結婚」以外の第3の解決策でも幸せになるには、問題自体の抽象度を変える必要があります。これについては、後で詳しくお話ししますね。
②問題のメリット
皆様は、そもそも問題にメリットがあると思いますか?
問題は苦の原因。デメリットのことです。だから問題はない方がいい→問題を解決しようとしますよね。
例えばビジネスは問題を解決することで人が幸せになって、その対価を支払うシステムかなと思います。
一般的には「問題」があるから「解決」ができる。解決すると喜んでくれる人がいる。その交換条件で成り立つ必要があるのです。
だから仕事をするには、困っている人がいないといけない。
不便を感じていたり、面倒くささを感じている人がいないといけない。
つまり立場を変えると、問題には、「自分が何かしらの価値提供をする」「自分の存在価値を満たす」ための活躍の場としてのメリットがあるわけです。
私たちは、問題を解決しようとしながら、問題を探している。
ここ数年、将来はAIにお仕事を取られるよ!と言っている人を見かけたり、それを聞いて怯えている人がいませんか?
こうやって問題提起することで、じゃあAIをやりましょうという仕事が売れたり、自分の仕事がなくなる恐怖を感じるからそれをケアする仕事がまた必要になります。
つまり今の人類にとっては、問題はあり続ける方がいいと考えることもできるわけです。
あとは、解決する必要のない問題さえも浮き上がらせる、という動きはSNSでもよく見ますよね。これがいいとか悪いとかではなく。
「今こんな症状がある人は、このまま放っておくと将来やばいよ」などと言って、問題意識を持たせて商品購入に繋げるために煽ることもあります。
それが「具体化」です。
何も問題を感じていなかったところに、「注目」を入れていく。
そうすることで「問題」は発生するんですよね。
例えば自分では体の不調に気づいていなかったけれど、自治体からハガキがきて病院で定期の精密検査をするとします。
そこで検査の数値を具体的に出すことで、病気が発見されるということはよくありますよね。
これってどうなんでしょう。
「気づいていなかったものが、発見できてよかったね。」
と捉えることもできるし、一方で
「数値を測ったことによって、自分は病気という具体性に注目した」
と捉えることもできるわけです。
つまり、決められた基準というのがあったとしたら、数値1メモリで、人は病気にも健康にもなれるわけです。
少しずつ、お伝えしたいことが明確になってきたでしょうか?
こう考えると、「問題のない世界」ってどうでしょう?
社会は、問題を解決しようとして成り立っている。
同時に、問題は生み出され続けている。
そして問題解決の精度が上がることが「社会の発展」にも繋がります。
広島から東京まで新幹線だと3時間半かかりますが、もし1時間でいけるようになれば、それは問題解決だし社会の発展です。
なので、解決すべき問題がなくなってしまうのも、考えものかもしれません。
この世界に問題が生まれ続けることのメリットが、社会にはあるはずなのです。
私は、このお話をして、物事が真実か嘘か、正義か悪かを問いたいのではありません。
私たちにとっての、問題の価値と、解決の価値について問いたいのです。
そして、問題とどう付き合って生きていくか?解決とどう付き合っていくか?を問いたいのです。
③哲学は問題解決を超えて問題消滅を起こす
ここまでで、「問題を解決することが社会的な価値の一つ」「問題にはデメリットとメリット両方がある」というお話をしました。
では、「問題を自己解決」できるようになったらどうでしょうか?
今までお話ししたように、問題を解決するには、「パズルのピースを合わせる」これが必要になります。
そしてもうひとつ、「問題消滅をさせる」方法もあります。
それが「パズルの抽象度自体を変える」ことです。
まず一つ目、
具体に注目して物事を解決する方法が、パズルのピースを合わせる解決法です。
例えば遠距離恋愛をしているカップルがいたとして、「会えないけれど会えるようにする」というのが具体での解決策ですよね。
次いつ会う?とか、どうやって会う?とか、会うために必要な時間やお金をどう解決する?というのがパターン1の解決策です。
また、夫婦関係が悪いとして、コミュニケーションをとったり、誤解を解いたり、また仲良しの夫婦に戻っていく方法を学んだり手に入れることも具体での解決策です。
具体に注目すると、パズルのピースを合わせる必要はあるのですが、ピーズがぴったり合うことで物事はどんどん解決していきます。
他には、パズルのピースをしっかり見れていない場合もあります。
例えば私たちの生きづらさは、過度な一般化で認知の歪みが起きることでも起こります。
「みんな私のことを嫌っている」
というような感想があるとしたら、「みんな」というのは過度な一般化です。
「彼は私のことを全部否定する」
というのも過度な一般化ですよね。
「みんな」って誰?
「全部」ってどれ?
そんな一般化に囚われていると、問題は起きやすいのです。
だからこそ、具体に注目する場合は、具体的な解決策を提示するか、丁寧に一つ一つの具体を確認して、自分と和解していくことが必要になります。
一方で、「パズルの抽象度自体を変える」という問題消滅の解決策は、例えるなら遠距離のカップルが目指している「2人の幸せ」自体の目的を捉え、今問題に思っていることの定義を変えていくことで可能になります。
夫婦関係についても同じです。
「方向性」や「一緒にいることの目的」自体を捉え、「仲良し」や「仲が悪い」「夫婦」「共に生きる」などの定義自体を問い直すことで、視座が上がり、問題そのものが消滅していきますよね。
例えるならビルの一階から街を見渡すか、ビルの30階から街を見渡すかで、見える世界は変わるイメージです。
一階にいた時に見えている問題の原因と、30階にいるときに見える問題の原因は、違うものになります。場合によっては、問題が問題ですらなくなるのです。
(このあたりがもし意味がわからないという方は、また補足を書きますので、教えてください。)
問題消滅については私が得意としているところです。
哲学は、抽象と具体を行き交い、物事の存在のあり方、定義そのものを問い直す営み。
そして愛は受容です。
この二つが合わさると、何が起きるでしょうか。
問題が簡単になくなっていきます。
白か黒か、正義か悪かで戦っていたところを、抽象化することで「白も黒も、どっちもいいね。どっちでもいいね。というかどっちも同じだね」となります。
白も黒も、結局は同じだったことに気づくのです。
毎日とても平和で、ストレスがありません。
しかし、それもまた極端だったのかもしれないと、最近思いました。
私は愛と哲学をやり続けることで、問題を認識することが減り、具体的な問題解決能力が著しく低くなってしまったのかもしれません。
そうなると、語らなければならないお話さえも、なくなっていく。
そして「なくなっていくこと」さえも受容することで、自分の役割というのはどんどん消えていくのです。
ただ、社会と溶け合っている。
しかし、大学のプレゼンでフィードバックをいただいたように、それが私にとって善でも、社会にとって善なのかどうかは、わからないわけです。
④問題とどう付き合っていくか?
今回、「問題を解決しようとする意思がなさすぎる」と意見をいただいたことで、私は自分のエゴに新しく気がつきました。
それは、「ジャッジは無くすべきだというジャッジ」です。
問題がなぜ起きるかというと、歪みが起きているかのジャッジをするからです。
歪みが起きていることに気がつかなければそこには問題はないし、歪みが起きていていいよね、と受容しても問題はなくなります。
だから私は長い間、自分のジャッジに気づいたらそこを柔らかくするというトレーニングをしてきました。
言い換えると、問題を問題として色濃く発生させることを、できるだけ避けていたのです。
そして、この記事の「救わないという呪縛」のタイトルのように、「救わない」というポジショニングに積極的に立とうとしていたことも発見しました。
社会で見かける「救う」という言葉にとても違和感があったからだと思います。
「別に救うべき人なんていないし、悩んでる人は悩んでいるだけの合理性があって、だから悩めば良いと思う。人を救いたいと積極的に言っている人に共感できない」
と、思っていたんですよね。
これは私の中に「救いたいと思ってはいけない」という明確なジャッジがあったんです。
もはや呪縛です。誰かのために何かをする、という時に「いかに救わないでいられるか」ということにこだわってしまうからです。
これが「極端」です。
エゴは両極に宿る。
「寛容」は「無関心」に転じることもあるかもしれないし、「問題意識」を持つことが、「神経質」と呼ばれる時もあるかもしれません。
毒は薄めると薬かもしれません。そして薬は、飲みすぎると毒になるのです。
右にいくか、左にいくかが問題なのではなく、過度であることが、執着になります。
問題を絶対解決しないといけないのはエゴかもしれないし、問題は絶対に放置した方がいいと思うのもエゴ。
「救おう」とするのもエゴかもしれないけれど、「絶対救おうとはしない」というのも、エゴです。
「より善く生きる」とはなんなのか。
その一つは、現代社会の抽象度に合わせて時流を読むということであり、共存することかもしれません。
抽象度を上げすぎたり下げすぎたり極端でありすぎるのも、また生きづらさを生み出す感じがしました。
別にジャッジをしてもいいし、しなくてもいい。
問題解決してもいいし、しなくてもいい。
救ってもいいし、救わなくてもいい。
私たちは目の前の出来事に、フィードバックをもらい続けているのだと思います。
変わっても変わらなくてもいいけれど、どうしても生き物は、変わっていきます。
何かを感じて立ち止まるのは、変化が必要なタイミングなのだと思います。
自分の美学やプライド、譲れない価値観を持つことは、素晴らしいことです。
だからこそ、起きていく出来事の観察者になりながら、変化し、より善く生きるヒントを得ていきたいですね。
もしよろしければ、皆様のご意見も教えてください^^
https://forms.gle/4Mq9Q4W8ax5MW4a9A



